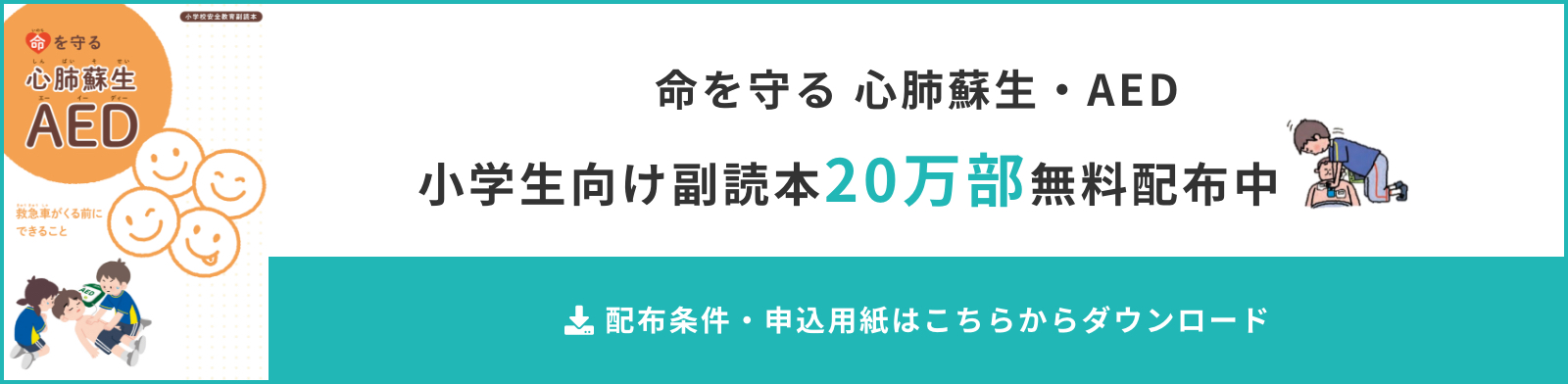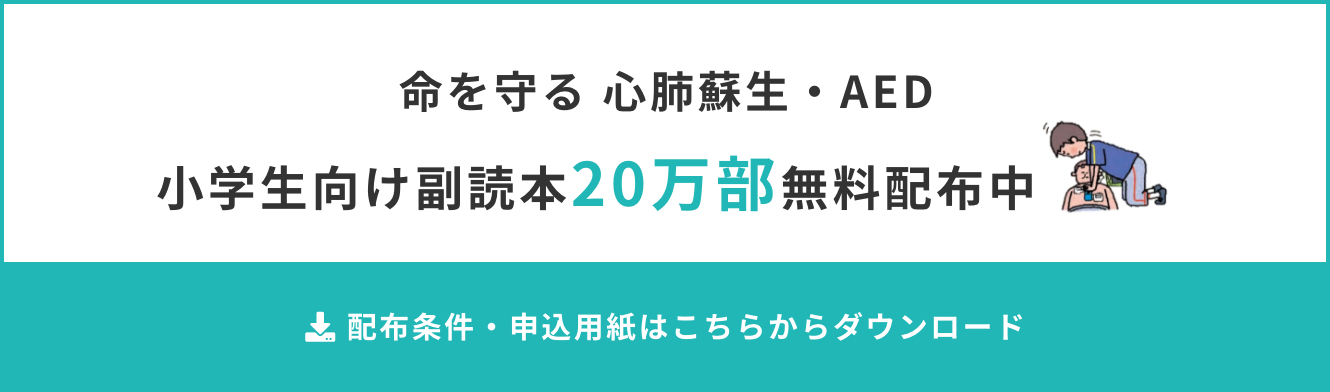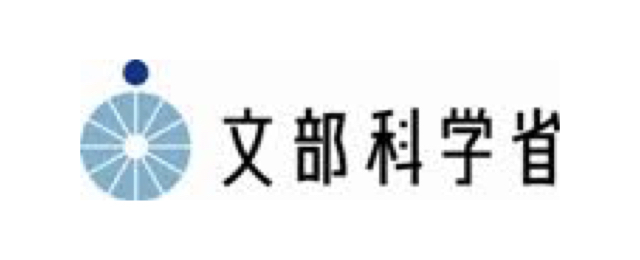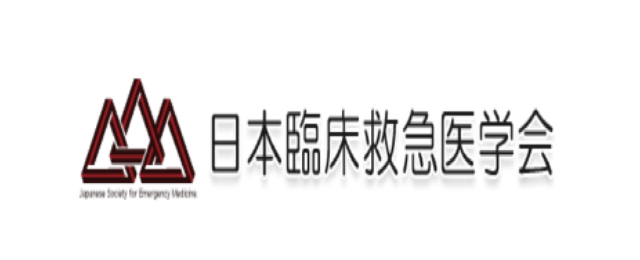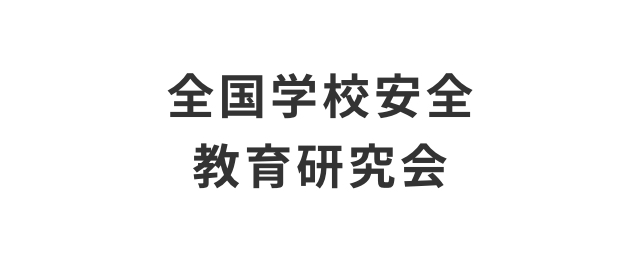学校での突然死ゼロ
School -学校での突然死ゼロを目指す-
- HOME
- School -学校での突然死ゼロを目指す-
Section
学校での突然死ゼロを目指した取り組み
- 突然の心停止発生時への
対応を含めた危機管理に関する具体的提案 - 小学校からの救命教育導入の促進
- 実践校の取り組み紹介や学校関係者への情報発信
これらの施策を通して、学校での突然死ゼロを目指します。

MOVIEAED財団の授業の実践例をご紹介
指導目標

指導目標は、児童・生徒の発達段階応じて、系統的・計画的に設定するのが望ましいとされています。以下に例を示します。
また、体験することは記憶の定着といった深い学びにつながり、それを繰り返すことで将来いざという時に行動できる自助・共助・公助が身についた人間を育てることができます。
完璧な実技の実施は求めませんが、小学校の段階から、命の大切さを学ぶ教育の一環として胸骨圧迫やAEDの使用方法といった実技を伴う教育環境を整備していきましょう
※「学年別到達目標例、心肺蘇生の指導方法、
指導内容に関するコンセンサス 2015(ver.160303)」
MENTAL STRESS
生徒・児童の
心的ストレスについて

心停止の現場に遭遇すると、心的ストレスを生じる場合があります。とても大きな心的ストレスを受けると、強い心理的反応:ストレス反応が生じる場合があります。具体的なストレス反応には、過剰な興奮状態、不眠、強い不安感、フラッシュバック、無力感、自責の念などがあります。これは救命処置に関わったか否かや、救命処置の結果にかかわらず、誰にでも起こりうるものです。心停止現場に遭遇した際に心的ストレスが原因でストレス反応が起こる可能性があることを皆が知り、支え合うことが大切です。
MENTAL HEALTH CARE心的ストレスを
抱えた際の対応
心停止の現場に遭遇した人のケアの体制を整えておくことも大事です。
特に、児童・生徒が心停止の現場に遭遇した場合は、下記のようなことが起こる可能性があります。
- 自分が心的ストレスを受けていることを理解できない、言葉で伝えられない。
- 大人が想像すること以上に大きく受け止めてしまう。
- 対処方法がわからないため、ストレス反応が強く出たり、異なった形で現れる。
- 不機嫌、乱暴になったり、怖がったり、ぼんやりすることが多くなる
- 心的ストレスを受けた出来事に関連する遊びや、
お話を繰り返す、夢を見てうなされる。 - 成長とともにその時のことを思い出し、数年経ってから症状が出現する。
- 大人よりもストレス反応による症状が長引く。
Q&A
AEDに関する、みんなの疑問や不安を解消します。
救命のための行動について
- 自分の完璧でない行動で悪化させないか不安です
- 完璧でなくても大丈夫です。なにもしなければ倒れた方は確実になくなってしまいます。
その時のあなたにできる行動一つ一つが、倒れた方の救命そしてその後の社会復帰につながるのです。 - わかっているつもりでも、いざという時に慌ててしまいそうです
- 人が目の前で突然倒れるというのは、日常想像していないできごとであり、だれもが慌てます。その時に大切なのは周りに人がいれば“協力”して救命にあたることです。また、前述したように救命行動は完璧でなくてもかまいませんので、慌てた中でもできることを行動に移しましょう。
慌てた時に、取るべき行動が1つでも多く頭に浮かぶよう定期的に救命講習を受講しておくことも大切です。
救命のための行動について
- 小学生への教育として救命教育は早すぎませんか
- 倒れた人が、救急車到着前に傍にいる人からなんらかの応急手当を受けていたのは50%程度しかないことがわかっています。大人になってから講習を受けるのではなく、義務教育の段階から繰り返し学ぶことが、将来救命のための行動につながります。また、学校は多くの児童生徒がいるため倒れる瞬間が目撃されやすく、 100%AEDが設置されているため救命されやすい環境にあります。
また児童生徒が第一発見者となる可能性が極めて高いことから、できることを知っておくことは大切であり、胸骨圧迫やAEDの使用の体験をとおしてその大切さを知っておくことも大切です。 - いざという時に救命に関わるよう教育することは、子どもには負担が大きすぎませんか
- 救命教育は胸骨圧迫やAEDだけでなく、命の教育も含まれています。「大切な人の命が突然止まることがある」ということを知っておくことは、「助けたい!」と思った時の行動の選択につながります。
また子どもに限らず、心停止の現場に居合わせたことで、その後強いストレスを感じることがあります。先生や家族には子どもを注意深く観察していただき、いつもと様子がおかしいようであれば話を聞いたり、専門家に相談するのも一つの方法です。 - 自分に自信がないので、教えるにも自信が持てません
- 救命教育となると、「医療=専門家でしか教えられない」と考える方が多いですが、ここで教えるのは“一次救命処置”であり、一次救命処置とは心停止に対して緊急で行う行動(119や胸骨圧迫、AED)を指します。これは一般市民にこそ行ってほしい行動であり、普及すべき内容です。よって、学校の先生には他の教科と同じように指導していただきたいのと、学校医などとうまく連携するのも方法です。
- 他のことでいっぱいで教育の時間が生み出せません
- 私たちは学校の時間の制約に配慮し、PUSHコースなどの短時間(45分や50分の授業時間で学ぶことができます)で効果的に学べる指導法を開発しました。また少人数で胸骨圧迫のトレーニングができるよう安価な教材の開発や、指導補助教材としてDVDなども作製・販売しています。
- 学校に教材や教具が十分にありません
- 現在はコンパクトで安価な教材が複数販売されています(PUSH&AED体験セット)。消防などでも貸し出していますが、前述した安価な簡易型教材を1~2人に1個用意することで、学校の授業時間に合わせて体験(胸骨圧迫やAED)を多く取り入れたプログラムを実施することができます。
©公益財団法人 日本AED財団 All Rights Reserved.